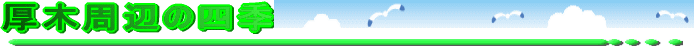

 |
ヒメアマツバメ |
 |
ドクツルタケ 日当たりの良い芝生の上に着陸したUFOのよう。ドクツルタケです。テングタケの仲間で”猛毒”を持つキノコとして知られています。カサの大きさは5cm~15cmぐらい、初夏から秋にかけて針葉樹林や広葉樹林がある所に発生するそうですが、本個体は芝生の真ん中に着陸しました。(5月21日) |
 |
ヒトツバタゴ。別名ナンジャモンジャ |
 |
里山のフジ 野生のフジが里山を彩っている。栽培され管理されたフジと違って野山のフジは勝手気ままに他の樹によじ登り樹冠を覆ってしまう。花が咲くと薄紫の霞がかかったようで遠くからでも春らんまんを満喫できる。(4月22日中荻野) |
 |
コブシ開花 寒い北国では山にコブシが咲くと春到来で、いきものが活動始める兆しといわれている。わが家のコブシはだいぶ遅くてサクラと一緒に開花するネボケコブシだ。ヒヨドリがめざとく飛来するがたくさんの花でどれから食すかまよって、結果どれもたべずに去ってしまった。(4月7日) |
 |
つばき 雪舟(せっしゅう) 島根県宍道湖北岸の野生ヤブツバキから選ばれた品種。一重の筒咲きで白い花弁と大きな雄蘂、黄色い花粉が美しい。「雪舟」という名は島根・益田に晩年蟄居した室町時代の画僧“雪舟”の名による。3月初旬ごろから咲き始めるがヒヨドリの来襲により花びらが喰いちぎられ無残な姿になる。蕾のうちに切り取り、茶席のいけばなとすれば清楚で純白な花姿から茶室は落ち着いた雰囲気となる。 |
 |
アカネスミレ Viola phalacrocarpa Maxim 乾きぎみの明るい丘陵地に点々と咲き、日本のスミレのなかでも茜色で華やかだ。 |
 |
ウラシマソウ Arisaema urashima H.Hara 長い釣り糸を伸ばして、浦島太郎の釣りざおを思わせる姿。テンナンショウの仲間は皆奇妙な花(仏焔苞)をつける。 |
 |
ミツバツチグリ Potentilla freyniana Bomm. 太陽に一斉に向かって「こんにちは」している。雑木林に葉が繁る前に花を咲かせ緑の葉をいっぱい広げていた。小野 |
 |
ヒメスミレ Viola yedoensis Makino 住宅団地の造成地にヒメスミレの群落があった。まだスギナぐらいしか進出していない裸地で太陽を独り占めしていた。 まつかげ台 4月10日 |
 |
ノジスミレViola yedoensis スミレによく似ているが、葉が少し広くふちが波打つヨレヨレの感じ。翼はほとんどない。スミレよりやや早く開花する。全草に微毛がある。日当たりのよい草地、駐車場のすみなどに生える。(08-4-4長谷)) |
 |
スミレViola mandshurica すみれと一般にいえばこのスミレが代表だろう。よくただのスミレと呼んだり、マンジュリカといったり。れっきとした種名だが広義のスミレとこんがらがる。葉はヘラ型で翼が明瞭だ。日当たりのよいところを好む。歩道のアスファルトの狭い隙間に生えたりと変なところが好きだ。(08-4-4毛利台) |
 |
スミレViola mandshurica 白花のスミレ。紫色のすじが残る。 シロガネスミレf.hasegawaeと呼ばれる物かもしれない。 (08-4-4毛利台) |