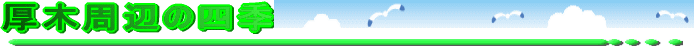
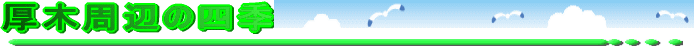

 |
�E�����J �Q�T�ԂŖ��J�ɂȂ�܂����B������͏��c�����ӂ̔~�тɑ����i��ʼnʎ����傫���~�����ɍœK�ȕi��̂悤�ł��B���W���������K��Ă��ē��₩�ł��i2��27���j |
 |
�V�W���E�J���̐����� �������X�C��������u���Ă���B�Ɋ��̓��X�������Ă��邪�쒹�����͑�����鐅���тɖK���B�����Ȃ����ƐS�z�����A�����ь�͏��̂����ʼnH��U��킹�Đ���A�g�����z���ɓ���������ڂ����ƌ��ߍ���ł���B(�P��25��) |
 |
���u�c�o�L ���u�c�o�L�̍��ݍ������}��I�肵���B���ꂢ�Ɏ��`�͐��������A���������Q���t�����}����������A���̂܂̂Ă�ɂ͔E�т����������B�K���X�r�ɂ��������Ēg���������ɒu����������1�T�Ԃقǂ��Q�͂ӂ���݊J�Ԃ����B��O�̃c�o�L�͊J�Ԃ���ƃ��W����q���h�����߂��Ƃ������ĉԖ������߂Ă��Ă��܂��ԕق͎S�߂ɏ���ł��܂��B�������p�͂Ȃ��Ȃ�������Ȃ����A���ꂪ�������l���L���Ȏ��R�{���̎p�Ȃ̂��낤�B |
 |
�K�K�C�� �H�Ɏ��n���Ċ������������B���ɂ͔����сi���сj�̐�������q����������B���{�_�b�ł́A�X�N�i�r�R�i�̐_���V�V�f���D�i���܂̂����݂̂ӂˁj�ɏ���Ă����Ƃ����A���ꂪ�K�K�C���̎���2�Ɋ����������ȏM�̂��Ƃ��Ƃ�����B ���̊��т̓P�T�����p�T�����Ƃ������A������͗T���ɂȂ��Ɠ`�����Ă���B�ł����O����Ǝ����Ă��܂������ŗv���ӁB |
 |
�c�`�C�i�S 12���ɂȂ��Ă��܂��������Ă���o�b�^�B�����Ƃ��ĉz�~���邪�A���������̓��������B�g�����z���܂�ł̂�т�߂����Ă����B���Ƃ��Ɣ�蒵�˂��肵�Ȃ��o�b�^�Ȃ悤���B |
 |
�c���A�I�J�����V ���N�A�e�n�ő�ʔ������ĉʎ����ȂǂŔ�Q���L�������B����܂ł͊��Ȑ��ɕ��z���Ă����悤�����A�����{�ł����ʂɌ�����悤�ɂȂ����B�n�����g���̉e�����B��A���ɏW�܂��Ă��ĉ����ɓ���Ƃ��̎n���ɂ͍��f����B�Ȃ�ׂ��Â��ɑޏo�肢�����B���̈��L�͂��܂�ł��Ȃ��B���̂܂ܗt���ȂǂŐ����z�~����炵���B |
 |
�C�^�` ���u�̉������҂����y��~���o�������Ƃ��č����猩�|����ꂽ�B�N�̎d�Ƃ��l�q�����邱�ƂƂȂ����B��J���~���Đ��Z���ƂȂ��Ă�����ƁA���ł���ȂƂ���ɏZ�ފ�l�͋��Ȃ��낤�Ǝv�����B�Z���T�[�J�������d�|���Đ�����ʂ��Ă����͉̂����C�^�`�������B����ȏZ��n�ɏZ�ݒ����ĐH�ו�������̂��B�G�H���Ƃ����邪�����ȍ������g�J�Q���炢�����Ȃ������B |
 |
�X�C�Z���@�劦���}���Ċ��������������������Ă��܂��B�J���~���Ď��x���オ������X�C�Z������ĂɊJ�Ԃ��܂����B�t�߂ɂ������肪�Y���Ă��܂��B(2024-1-22) |
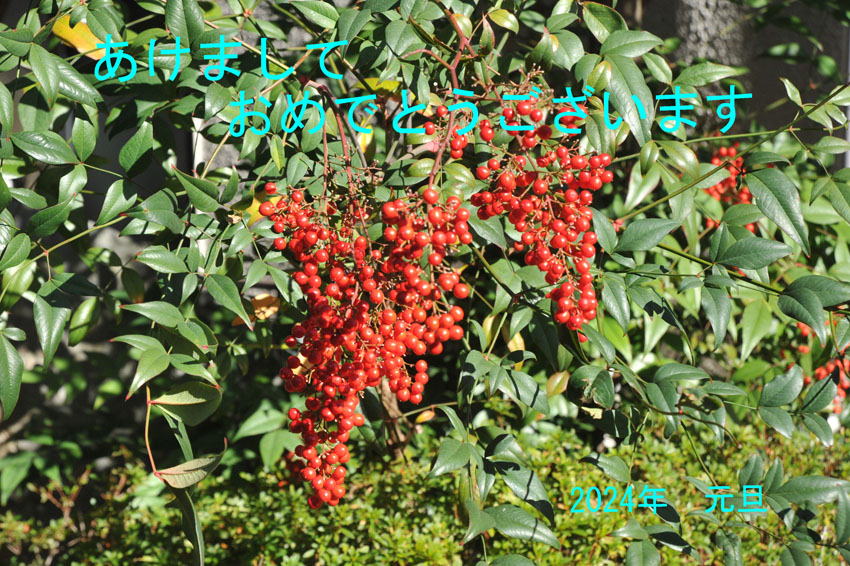 |
�i���e���@ �@�i���e���͢���]���飂ƌ����A�Â����牏�N�̗ǂ��A���Ƃ��Ēm���Ă��܂��B�݂Ȃ��ܕ��ɂ��{�N��̂Ȃ������ȔN�ł���܂��悤�F�O�������܂��B�쒹�͓~�A��R�ɐH�ו������Ȃ��Ȃ�ƍŌ�ɐ^���Ԃȃi���e���̎���H�ׂɗ��܂��B(2024-1-1) |
 |
���T�V�A�u�~ �֓��n���ɂ͎������Ȃ��ƌ����Ă��܂����A���̍�����킪�ƂŔ��肵�đ傫���炿�܂����B�����t���āA���n�����̂͐��N�Ԃ�B�����͖쒹�ɐH�ׂ�ꂽ��A���n�܂łɎ��炸�͂�Ă��܂��Ă��܂����B(2023-12-7) |
 |
�L�^�e�n |
 |
�t�L�m�g�E�@�@�����m�݂��ݒ�C�����ʉ߁B���x�o��Ȃǐg�\�������A�����͉����ŋC�����}�㏸�A�t����C�ɋ߂Â����B�t�L�m�g�E���t��҂��]���傫���ӂ����ŗz�������ς����тĂ����B�i2��11���j |
 |
�����T�L�V�W�~�@�@���̕\�����F�ŁA���͂������F�ʼn�����Ă���������`���E�ł��B�����ʼnz�~���A�N3-4��A6�����痂�N3���ɂ����Č���܂��B�G�ؗсi�A���J�V�сj�₻�̎��ӂŌ����܂��B���������������A�����������L���đ̉����グ�Ă��܂����B�����Ƌ߂Â��ĎB�e�����݂܂������������܂����B(2023-1-27) |
 |
�c���E�����h�L�@�Ԃ������p�����킷�܂ł͒n���Ȃ�A�����B�����Ԃ̍ޗ��Ƃ��āA���̎����ԉ�����ł��l�C������B�쒹���G�T�̏��Ȃ����̋G�߁A�q���h�����͂��߃��W����W���E�r�^�L�Ȃǖ������X�ƏW�܂�B |
 |
�L�^�L�`���E ���F�����̐g�߂ȃ`���E�B���̕\�ʂ��قƂ�lj��F���Ȃ��Ă���̂ł��̌̂͏H�^�B���ʂɂ͍����F�̏����Ȕ��_������A���������F�ɂȂ��Ă���B����������̑��ނ�Ȃǂɐ�������B�t������11�����炢�܂Ŕ������A�H�͉̌̂z�~������̂�����B�c���̓n�M�A�l���m�L�Ȃǃ}���Ȃ̐A����H���Ƃ���B(2022-12-27) |
 |
�A�J�G�O���o�@(���K�ȁj �t���Ɏ����������A���H���̂悤�ɂ�������ꂽ�O���A����݂�قnj����ȋ[�ԁB �g�t���I���Ԋ��F�̌͗t��ԂɂȂ����t���ς�������B��قǒ��ӂ��ώ@���Ă��Ȃ��ƕ�����Ȃ��B���R�̎G�ؗт̉��Ō������B�����z�~���c���̓c�d���t�W�ȁi�A�I�c�d���t�W�j�̗t�����ׂ�B(2022-12) |
 |
�C���n���~�W ���L���L���܂������A�킪�Ƃ̎��������ɍg�t���܂����B�g�������������A�_�����ȂƎv���Ă��܂����B�Ă���̕��͎S�߂Ȍ͂���ł������A�}�ɗ₦���邪����A�܂������o����l�q�ƂȂ�܂����B�i12��12���j |
 |
�C�k�R�����i�M�@�g�������������������B��������ǍD�̃C�k�R�����i�M���ԉ���}���ɑ傫�������B �i�������ǂ��̐X���� 2��25���j |
 |
20�p���炢�����钷���`���n�`�̑��B�G�ؗт͎̌}�ɒ����Ă����B�Z�l�i�Z�n�`�H�j�͋��Ȃ��B����Ȓ����I�̑������͉̂��҂��낤�B�z�\�A�V�i�K�o�`�̑����������B�z�\�A�V�i�K�o�`�ɂ́A�q���z�\�A�V�i�K�o�`�ƃ������z�\�A�V�i�K�o�`�̂Q�킪���邻�������������ł͂ǂ��炩������Ȃ��悤���B |
 |
�Z���_���@�@�g�n�̊C�ݗт◢�R�ɐ����闎�t�����B�����n�͈ɓ������Ȑ��ƌ����Ă��邪�e�n�̊X�H������A�w�Z�ȂǂɐA�͂���Ă��āA���R���z�͕s���̂悤���B���t�������ƒ��������������Ɏc���Ă���B�~���ꣂƂ��đ傫���}���L���Ă���p�͎v�킸���グ�Ă��܂��B�i2021,2,2�j |
 |
�G�ؗтŊ�ȕ��̂��������B���҂Ȃ̂�? �Y�[��g�Y��ł����Q�������B�j���g���̗��قǂ̑傫���B�u���u���Ə_�炩���B�w�r�̃^�}�S���Ƃ��h�J�b�p���q���q�h�̃^�}�S�Ƃ��c�A�����Ăɏ��������o����C�����荬�����Ă����B�J�b�^�[�i�C�t�Ŕ����ɂ�����[���[��̕��̂������B�ŁA�悤�₭�����B�u�X����̎莆�v������1995�@�ɏo�Ă����B�X�b�|���^�P�c�ۂƁB�X�b�|���^�P�ɂ��Ă̓l�b�g�Œ��ׂăl�B |
| ���Y �l�����Q�b�g�����悤�ł���B�i2015,1,1�j |
|
 |
�����^�e�n �~�̖쌴�͐������̂����Ȃ��₵���B�z�~���̃����^�e�n���g�������ɕ����Ă����B(�P���Q�T���ڂ������̋u�����j |
 |
�V���o�V���i2014-1-11�j ���~���̕����B���ꂽ�������łȂ��ƌ����Ȃ��B �V���o�V���ɒ��������B�A�Y�}���}�A�U�~��R�E���{�E�L�̌͂ꂽ�s�ɂ��������Ă����B�i�{�����j |
 |
�V���n��(2013-1-16) �����t�������Ē��T���B�Ȃ��Ȃ����邢�Ƃ���ɂłĂ��Ȃ������B |
 |
�A�I�W�i2013-1-4�j �ӂ���̓��u�̒����ړ����Ă���A�l�O�ɏo�ė���̂͂܂�B |
 |
�A�u���R�E���� �~�����Ă���͂��̃A�u���R�E���������킪�Ƃ̎��ӂŊ������Ă����B����ӁA�O�����̃o�P�c�̐����������Ƃ����̂��ė����Đ������Ă��܂����B�i2012-2-10�j |
 |
���h���M �P���L�̑�̒���t�߂Ɋ��Ă����B�P���L�ɗt���ɂ��Ă���ƕ�����Ȃ����A���̎����t�𗎂Ƃ������ŗ�����A�o�ዾ�ł̂����ƁA�ǂ��݂���B�W�{�͋����̌�ɂ䂭�Ɖ��ɗ����Ă���B�i07-1-7 �ɐ����s���䑽�_�Ёj |
 |
�N�`�i�V�i�A�J�l�ȁjGardenia jasminoides �H���炸���Ƃ��̎p�B�I�L���g���̒��F�Ɏg���B�������Ղ̑��̌`�����̃J�^�`�B���q�@�䕨�̌�Ղ̑��͂܂������Ȃ��^�ɂȂ��Ă��Ȃ������B�l���A��B�ɃR�����N�`�i�V���������邪�A�_�ސ쌧�ł͂��̕ώ�N�`�i�V���������Ȃ��B�i�O�U�N�Q���S���@����@�A�́j |
 |
�V�i�}���T�N(�}���T�N��)�@Hamamelis �t�ɐ�삯�āg�܂��炭�h�̂Ł\�\�}���T�N���������B���̉Ԃ������Ȃ��Ō�����ƃz�b�Ƃ���B����݂͗��t�����܂��܂����������Â��B�V�i�}���T�N�͌͗t���t�����܂܉Ԃ��炭�B�i�O�U�N�Q���S���@����@�A�́j |
 |
�~�c�}�^�i�W���`���E�Q�ȁj Edgeworthia chrysantha �a���̍ޗ��ƂȂ�̂͂��ׂ̍��}�B�K���O�ɕ������B�Ԃ�t���Ȃ��Ƃ������ɔ��ʂł���B�������Y�B �i�O�U�N�Q���S���@����@�A�́j |
 |
�t�L�m�g�E �@�����m�t�L�̉ԁB�����~���I�邱��Ԃ��炩����̂Œ��d���邪�A�t���i�s���L�тĂR�Ocm�قǂɂ��Ȃ�ƒN�������������Ȃ��B���N�͊��������������Q�T�Ԃقǒx�ꂽ�B���t�̖��o�Ƃ��āA���̂ق�ꂢ�������Ƃ���B�i06-2-27 �����j |
 |
�V�L�U�N���i�o���ȁj �q�K���U�N���̉��|��B11�����납��炢�ĉԊ��͒����B�~�ɍ炭�Ԃ͏������ԕ��͒Z���B�ʖ��W���E�K�c�U�N���B �i2��3���@�ɐ����E�O�m�{�j |
 |
�E�� ���N�̓E���̊J�Ԃ������ƕ������A���؎��ӂł͗�N�Ƃ��܂���Ȃ��悤�ȋC������B�����i��ł��J�Ԃ̌덷�͑啪����B�傫�ȉʎ����Ȃ颔����ꣂ��ǂ����̓�����g�������ł͍炫�������B�i2��3���@�ї���j |